
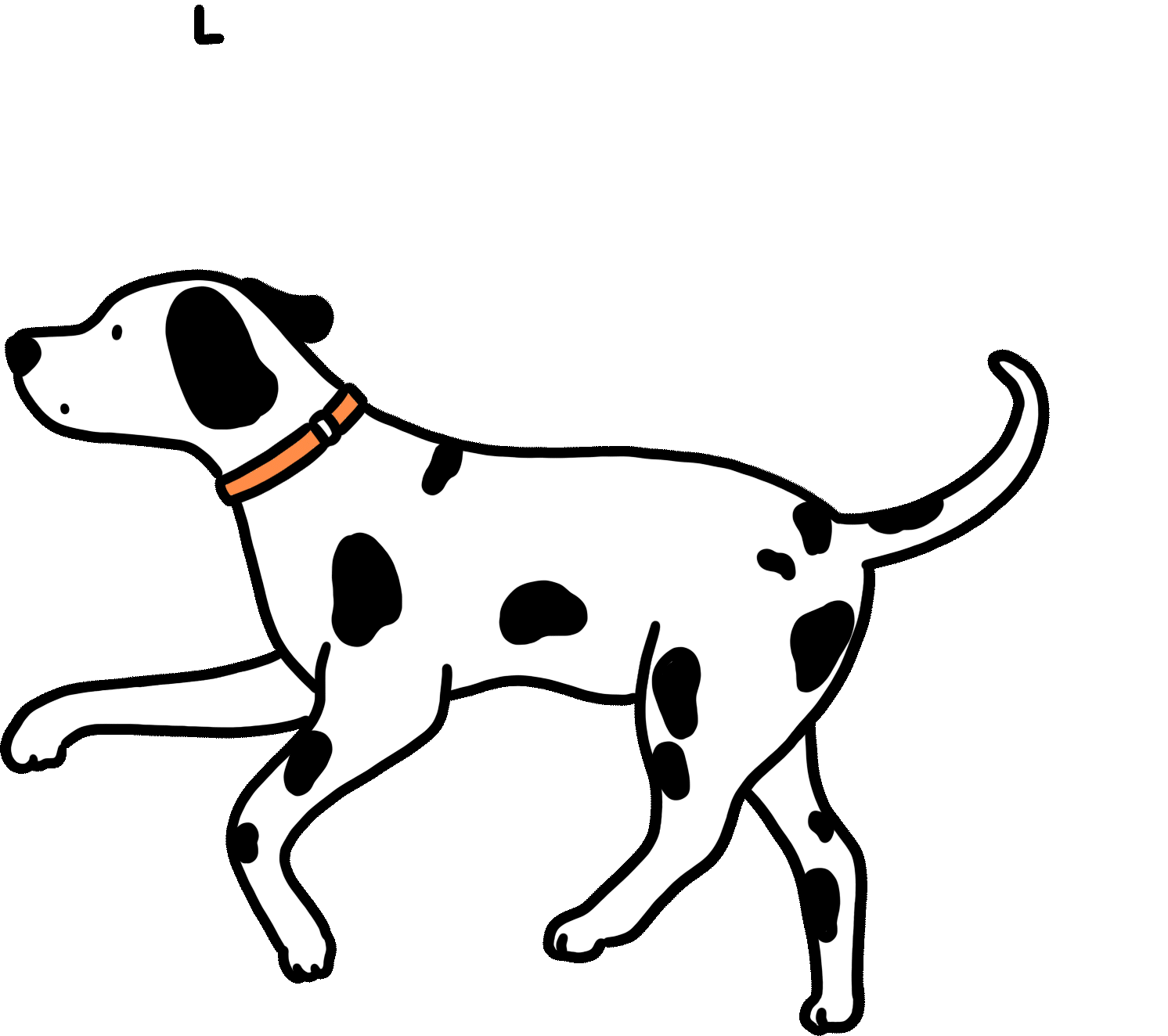
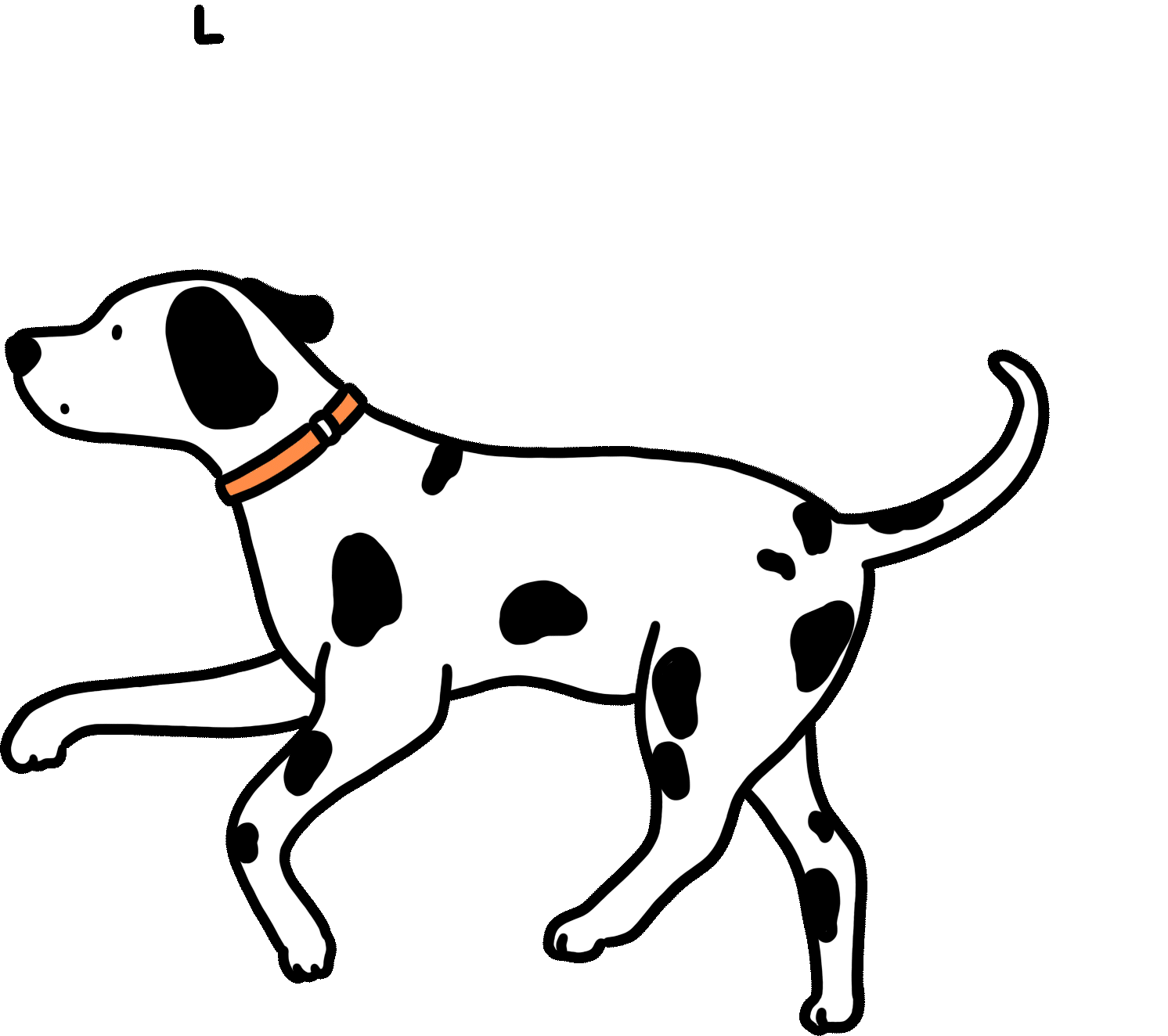

東京発の世界的アイウェアブランド YUICHI TOYAMA.。
伝統と革新を融合させ、数々の魅力的なプロダクトを生み出してきました。その洗練されたデザインは、ジョルジオ アルマーニをはじめとする有名ブランドからコラボレーションのオファーが寄せられるほど。国内外のファッション愛好家や眼鏡ユーザーからも高い評価を受けています。
実は、GEN社内にも多くのファンが存在しており、今回インタビューを担当したBrand Director 武藤もその愛用者の一人です。なぜ、YUICHI TOYAMA.はこれほどまでに美しい眼鏡を生み出すことができるのでしょうか。
前編では、YUICHI TOYAMA.誕生の背景、そして創業者である外山雄一さんが大切にしている仕事の哲学について、じっくりお話を伺いました。

父はカメラマンで、小さい頃からその仕事ぶりをそばで見て育ちました。 カメラや被写体の位置を1ミリ単位で調整し、何度も撮り直す姿を見て、「こんなの絶対無理だ」と当時は思っていました(笑)ところが気づけば、自分も眼鏡の図面を描くときに、コンマ2ミリ、コンマ3ミリの世界で仕事をしているんです。今の仕事に就いたのは、父の姿を見ていたことが少なからず影響していると思います。
高校時代には、左官屋さんの現場でアシスタントをしていました。その経験を通じて、“職人”という存在が自分の中でぐっと大きなものになった気がします。“手に職を持つ”人たちの姿に、どこか憧れがあったのかもしれません。
転機となったのは、ヒップホップとの出会いです。中学・高校時代からずっとヒップホップを聴いていて、Run-DMCの来日公演には大きな衝撃を受けました。あまりの衝撃に、それ以来ヒップホップを軸にファッションやアートを捉えるようになったんです。グラフィティアートを模写したり描いたりするうちに、「立体を頭で想像する面白さ」に気づきました。そこからプロダクトデザインへの興味が広がっていったんです。
当時のラッパーやR&Bシンガーがジャン=ポール・ゴルチエのサングラスをかけているのを見て、「なんて格好いいんだろう」と憧れました。映画『イージー・ライダー』で俳優がかけていたレイバンのオリンピアにも心を奪われましたね。もともとはアイウェアを“ファッション”として捉える部分が強く、最初に就職したのも有名メゾン系ブランドのライセンスビジネスを扱う会社でした。
しかし、仕事を通じて福井県の眼鏡職人さんたちと接するうちに、その工芸的・民藝的な側面にどんどん魅了されていったんです。いわゆる“名もなき職人”たちが集まる福井県鯖江市では、伝統技術をベースに素晴らしい眼鏡が作られています。ものづくりや職人技への憧れが深まり、気づけばどんどんのめり込んでいきました。

2004年にフリーランスのデザイナーとして活動を始め、2009年に自身のブランド「USH」を設立。2017年春夏コレクションからは、「YUICHI TOYAMA.」として活動しています。
ブランドとしては、大きく分けて「YUICHI TOYAMA.」と、そのプレステージラインである「YUICHI TOYAMA : 5」、そしてサングラスラインの「mille(ミレー)」があります。
「mille」は一見すると女性向けのサングラスラインと思われるかもしれませんが、実際は“女性向け”というよりも、女性に好まれる色合いを比較的多く取り入れている、という感覚です。僕たちは「YUICHI TOYAMA.」も「mille」も、あまり性別でカテゴリーを分ける必要はないと考えています。
昔からユニセックスな視点を大切にしており、年齢や性別を問わず誰もが楽しめるものづくりを目指してきました。お店の内装やブランドの雰囲気も含め、「中性的なイメージ」を大切にしています。
ニュートラルな佇まいの中にも「自分たちらしさ」を追い求めた結果、たどり着いたのが「ダブルダッチデザイン」です。このデザインがここまで美しく仕上がるのは、日本の職人さんたちの高い技術力があるからこそ。決して簡単には真似できないものです。

似たようなデザインは結構出回っていますが、これほど美しく七宝塗りで着色できるところは他にないですね。
やはり、職人技と自分たちのデザインがうまく組み合わさることで、唯一無二の価値が生まれるんです。そこに、この仕事の一番の意義を感じています。

「YUICHI TOYAMA.」というブランドで大切にしているのは、自分にしかできないデザインを形にし、職人さんたちと一緒に、今まで誰も見たことのないものを作り上げていくこと。その考え方から生まれたのが、プレステージラインである「YUICHI TOYAMA : 5」です。

30年間、眼鏡をデザインし続ける中で、「何が本当にカッコいいのか?」と試行錯誤しながら、少しずつ答えを見つけてきました。若い頃はトレンドの最先端を追いかけることもありましたが、よく考えてみると、眼鏡そのものが主役ではなく、それをかける人が主役なんです。だからこそ、その人が最も自然体で、カッコよく振る舞える“導線”となるデザインを目指すようになりました。

そうそう。車好きの人が愛車を磨いている姿なんかも、すごくいいですよね。 「高級車に乗っているかどうか」じゃなくて、「その車を愛でている姿」のほうが、ずっとカッコいいと感じるんです。
じゃあ、眼鏡におけるそういう“愛でる”行為って何だろう?と考えたとき、たどり着いたのがセルフメンテナンスでした。そこには、デザインを超えたカッコよさがあるんです。仕草そのものが美しくて、いわゆる“用の美”と呼ばれる美しさにも通じるものですね。
やっぱり、使いやすさから生まれるデザインこそが一番美しい。 僕なりにそれを表現するなら、まずは眼鏡の壊れやすい部分へのアプローチでした。友人の中にも、レンズが外れたり、丁番のネジが取れただけで「壊れた!」と慌てる人がいるんです。でも実際は「いや、ネジをはめ直せば直るよ」と伝えると、「え、そうなの?」って驚かれることが多いんですよね。
だったら、誰でも簡単にネジを回せる仕組みを作ろうと考えたのが出発点です。 普通の精密ネジって、100円ショップのドライバーだとすぐ“なめて”しまう。ネジ山が潰れて回せなくなるんです。そこで「どうすればネジが“なめ”にくくなるだろう?」と考えたとき、ふと思い出したのが六角レンチでした。
職人さんに相談しながら、そのアイデアを形にしていくうちに、「自分でセルフメンテナンスできる眼鏡を作りたい」という想いが具体化していきました。

作り手である職人さんたちはまさに“達人”です。こちらもデザインやクリエイティブの分野で“達人”でなければ、彼らの技術やポテンシャルを最大限に引き出すことはできません。
クリエイティブに対して常に貪欲で、職人さんに「なるほど、これなら」と納得してもらえるようなデザインを提案することが、自分の使命だと思っています。
ファッションの世界には華やかさやトレンド性が存在しますが、それだけに特化すると、消費されて終わってしまうこともある。そうではなく、僕は時間を超えて長く愛されるものを作りたい。だから職人さんと対等な立場で意見を交わし、お互いを高め合うことが、本当に魅力的なデザインを生み出すために欠かせないと考えています。
ヴィンテージフレームのように、すでに“歴史”を背負ったものにはかなわない部分もあります。でも、僕たちは職人さんたちの技術を活かして、新しいデザインを生み出すことで“これからの歴史”を作ることができる。
そうですね。個人的には「フレームがすごく気に入ってるから、レンズが合わなくなったら交換してでも使いたい」と思ってもらえるような眼鏡が理想なんです。長く愛せるものを作りたいんですよ。
実際、同じモデルの色違いを買ってくださる方もいるんですよ。本当に気に入ってもらえているんだなと感じられて、デザイナー冥利に尽きます。もちろん新しいモデルも常に発信しているんですけど、僕らは生半可な気持ちで作っているわけじゃないので、「ずっと使い続けたい」と思ってもらえるような普遍性をちゃんと見つけられた、という答え合わせにもなるんです。

僕にとってのキーパーソンは、試作を担当してくれている職人さんです。僕が描いたデザイン画を実際の形に起こしてくれる方で、もう30年ほどの付き合いになります。前の会社でも一緒に仕事をしていて、今はフリーランスとして活動されていますが、僕の好みをよく理解してくれているんです。「外山くんなら、この角はこう丸めたほうが好きだよね」と、細かい部分まで自然に察してくれるんですよ。
そうなんです。仕事をする時は、まずはその試作職人さんと一緒に金型を作ることから始めます。プレスという工程が非常に重要で、金型ひとつでパーツの完成度が大きく変わってくるんです。ネジ、試作、金型、部品、七宝、仕上げといったさまざまな工程を経て、ようやく一本の眼鏡が完成します。
試作品をベースに少しずつ形を決めていくんですが、実際におかけいただいている眼鏡も、もとは試作品を削ったものなんです。完成品に近い状態から改良を重ねて仕上げたのですが、試作品とは思えないほど美しいでしょう?
試作があることで、金型を作る際の表情やメタルの丸みなどを具体的にイメージしやすくなります。金型は本当に重要な工程なんです。
アセテートの場合は、厚みのある板から直接削り出していきます。ごっそり削って、磨いて、また削って、さらに熱を加えて模様を入れ、そこに丁番を取り付ける……と、本当にたくさんの工程が必要です。誰か一人が手を抜けば、良いものは決して生まれません。ここにはやはり工芸的な要素があって、「みんなで協力して美しいものをつくる」という感覚が大きいんです。

確かに、「もったいない」という感覚が文化として根付いているのは大きいと思います。物を無駄にせず、必要以上に捨てないという意識は、日本人の中に少なからずあるのではないでしょうか。
四季の変化や気候など、さまざまな要因が影響していると思いますが、もともと日本は農耕民族です。天候によって収穫が左右されたり、神様にお供えをする習慣があったりと、自然と共に生きる文化の中で育まれてきた感覚です。 そうした背景のもとで、「機能を最小限にまとめる」という発想や、「用の美」という概念が生まれてきたんだと思います。

GEN(ジェン)は事業規模を問わず、様々な業種・業態のニーズに合わせてご利用いただいております。お気軽にご相談ください。スペック表/料金表/各種資料のダウンロード、ShowRoomでの製品デモ予約や無料トライアルも受付しております。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されておりプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。