
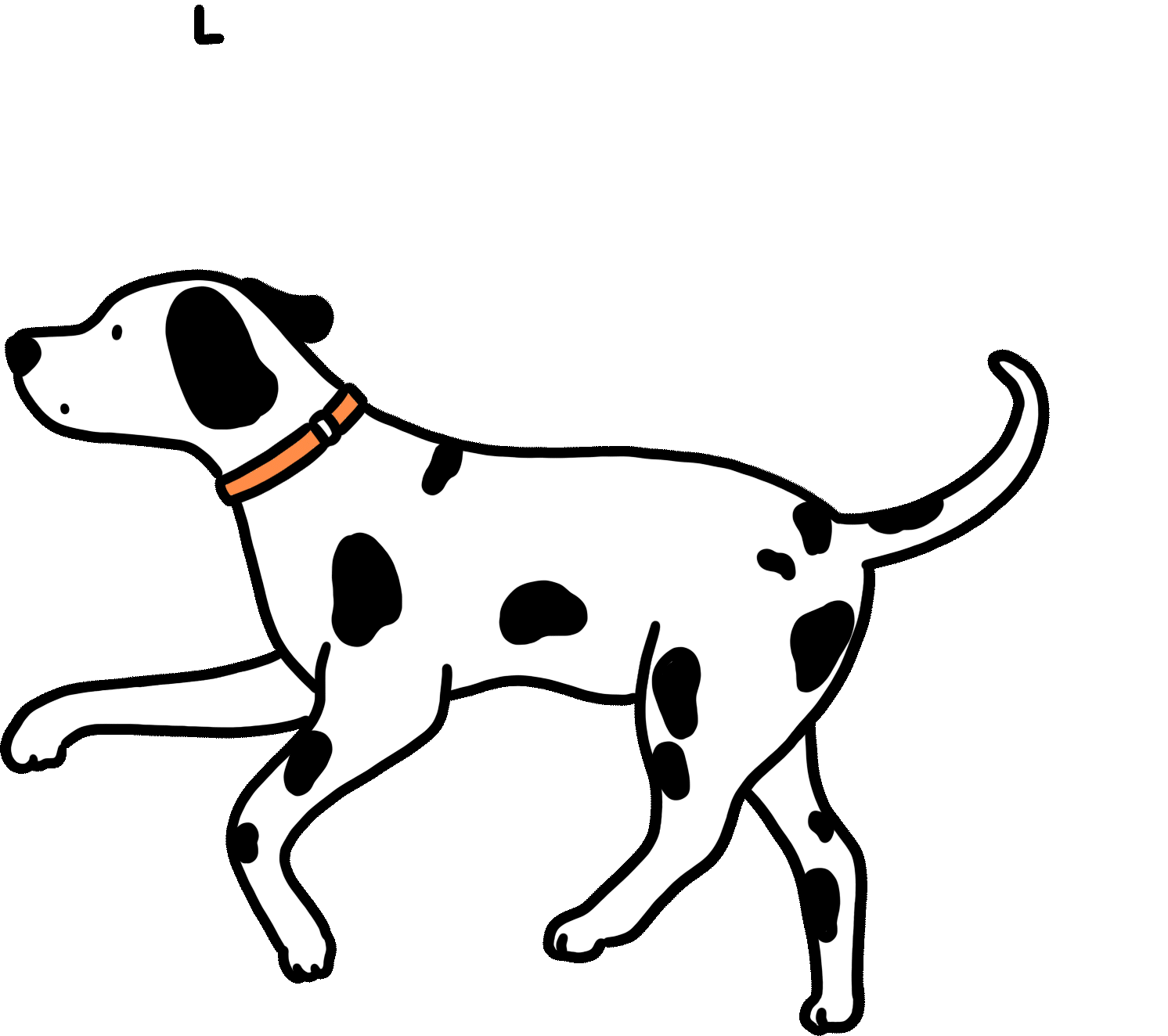
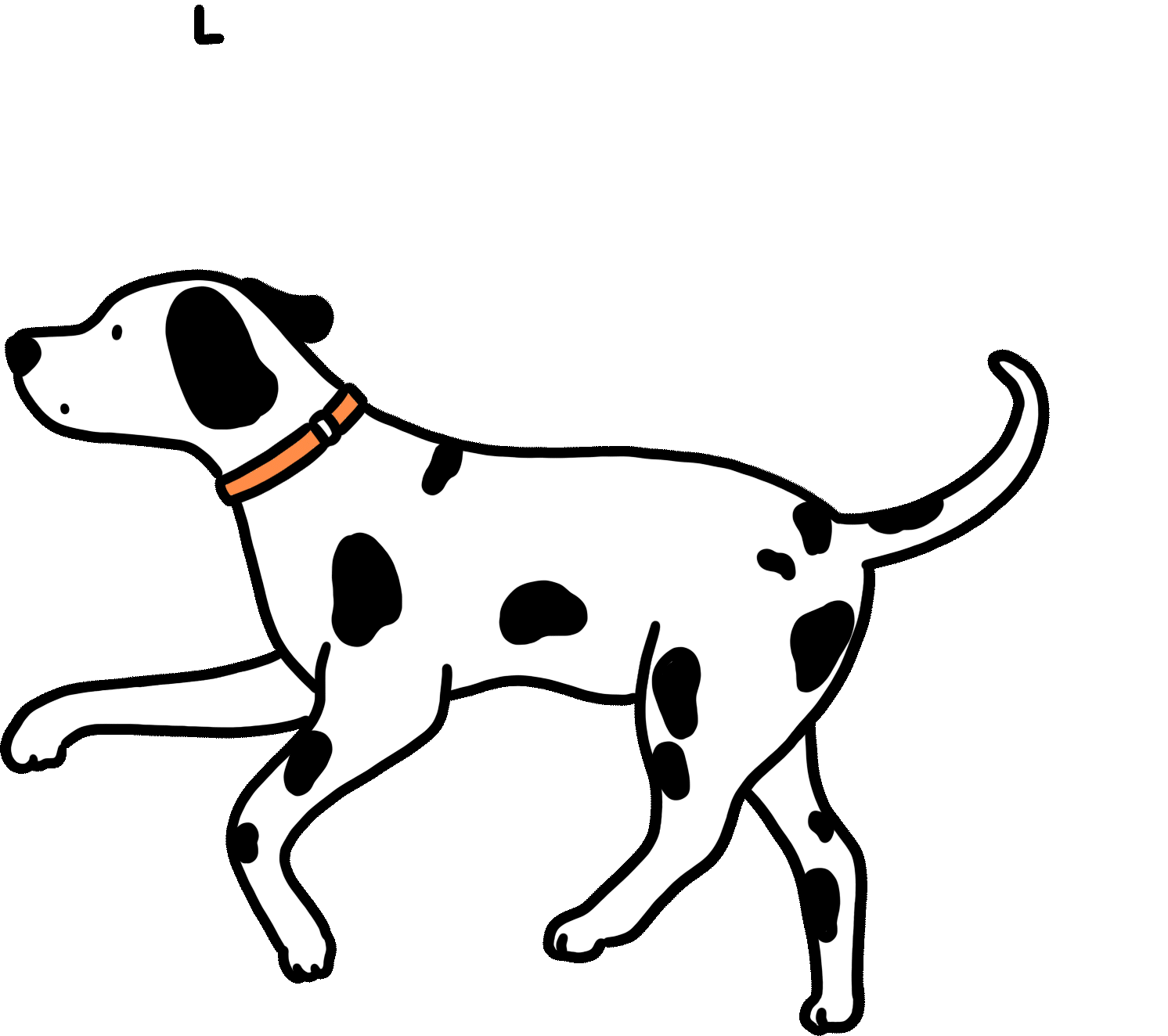

前編では、太田さんのワインとの出会い、ヴィナイオータ立ち上げまでの経緯、そして太田さんがなぜワインそのものや造り手に魅了されたのかをうかがいました。
後編では、どのように太田さんが自身のフィロソフィーを仲間に伝え、カルチャーを作ってきたのか…オフィスや食堂、ヴィナイオータの活動全てで表現する哲学をお話しいただきました。
スタッフに対して頭ごなしに何かを言うのは好きではないんですけど、唯一NGワードが存在するとしたら「悪い年」って言葉ですね。
天候的には恵まれてない年でも、偶発的に面白いものが生まれることもあります。例えば貴腐ワイン。貴腐菌がついてるようなブドウって、一見するとすごく汚いんですよ。カビが生えているんだから当たり前ですよね。だけど、貴腐が妖艶なワインを造ることもあるんです。

左:取材に立ち会うことの多いマネージャーの五月女さん”太田の話は誰にでもいつでもブレない(笑)”
なりがよくて健全なブドウが多く取れるなら、それに越したことはありません。でも、雨が多かった年は、シュッとした薄いワインでいいと思うんです。だって、そういう年だったんですから。
薄さの向こう側に「大変な年だったのかもしれない。だけど、きっと造り手のこの年のベストが込められてるはずだ」と思いを馳せ、想像する力があったら、もうただただ、有り難くワインをいただけると思うんです。
だから僕は飲み手の人たちの想像力を膨らませるお手伝いをしたいと思ってます。もっと知らないことがたくさんあると気づいてもらいたいし、リスペクトや思いやりみたいなものを、自然やワインの造り手、土地に対して少しでも持てたのならば、実生活にも良い影響があると思うんです。

地下セラーの上部に立つ自宅兼事務所は地域の木、資源を活かした「里山建築」
ワイン業界におけるナチュラルワインの立ち位置が変わり、その中でヴィナイオータの立ち位置もできてしまい、会社も拡大しました。
抽象的な話をすると、筋肉や関節がうちの各スタッフだとするのならば、そこにほんの少し脳を持たせないといけないんです。
脳が発した指令ぐらいでは多分、モビルスーツはナチュラルに動かすことができないんですよ。動きをつかさどる大事な部分に、僕とほぼ同じような意識とイメージを持ってもらわないといけない。
最初は「ワインが美味しくて好き」だけでいい。だけど、その美味しさの向こう側に、造り手がどれほどの思いを込め、苦悩や失敗を経てきたのか、こっち側に来たら想像できるようになってほしいですね。
今の先進国のライフスタイルを続けていくには、地球に限界がきていることはわかってるはずなんです。人類の存亡が、農業のあり方の中に既にあると僕は思ってるんですよ。だから、それに気づいて、共感してくれる仲間を増やしたいです。



だだ商店 だだ食堂では厳選された食品と、農業部が栽培した野菜が並ぶ
だだ食堂は午前11時に開店し、午後7時まで営業しています。ランチ時間を外しても、ご予約していただけたら、ちょっとしたお料理をお出ししたり、ゆるっと食事ができる空間なんですね。
でも、この店の一番の持ち味は、膨大な量のワインです。夜のレストラン営業ができるようにならないと、宝の持ち腐れになっちゃう気がするんですよ。
セラーのワインをリスト化して公開したら、きっと驚かれる方も多いと思います。海外から売ってくれと問い合わせが来るようなレベルのものも含まれます。

「だだの地下」に眠るお宝のようなワインの一部
だけど、僕がやりたいのは、ワインを高値で売ることではなく、ヴィナイオータに来て、ワインを開けて、飲んでもらうことなんです。それは、転売のリスクを防ぐことにもつながります。
造り手が数千円でヴィナイオータに売ったものが、うん十万円で転売されてしまう危険もあるんです。造り手が数千円しか儲けてないのに、その1本から十数万円取ってる人がいるなんておかしな話ではないでしょうか。心がこもってるものなだけに、そういう扱いをされることだけは防がないといけません。
だから、良いワインをしっかりと寝かし、適正な価格で飲んでいただくことを、お店でやりたいですね。そのためにも、僕の無茶ぶりに応えられる凄腕料理人を募集中です(笑)

ランチのラビオリ(※取材時)は太田さんが現地で食べた味を再現したもの

身の回りにあるものをできる限り自分たちで作れるようになりたくて、加工場を作りました。石臼の製粉機、ジェラートや焼き菓子を作るための設備や大きな厨房があります。
僕たちがどんなに無農薬で小麦を作ったとしても、製粉所の製粉機についてる小麦粉に残留農薬があったら、どうしてもちょっと混じっちゃうじゃないですか。だから製粉場を選ばないといけないんです。
さらに小麦のように原価が安いものに送料をかけると、どうしてもコストが跳ね上がってしまいます。製粉所には、ある程度の量を送らなければ採算も合いません。
自分たちで製粉機を持つことで、来歴が確かなものしか臼の中には入ってない状態を作れますし、挽く量も自由に調整できます。


そうですね、やっぱりワインは食事と一緒に楽しむべきものですし、気のおけない仲間と飲んだらもっと味も良くなるかもしれません。
お店作りで僕が意識したことは、食べ心地の軽さ、飲み心地の軽さ、居心地の良さの三つなんですけど、全て“心地”の話なんです。全部がある空間を目指しました。
あとどうしても、インポーターという職業柄、一般の方と直接コンタクトを取る機会が少ないんです。お店を持つことで、お客さんと直接対話ができる場所を実現したかったのも大きいです。

インポーターは、ワインの造り手の日本駐在大使だと思うんですよ。無償の愛で造り手とワインの良さを伝えていかないといけない。それがインポーターとしての仕事で一番大事なことですね。 そしてもう一つ大切なのは、いかにワインをバリアフリーにできるかです。自分の権威を守るためにワインを小難しいものだと思わせている人が、残念ながらこの業界にはたくさんいます。僕はそんなもの全部壊して、どこまでも平らにしたい。ワインが大好きだから、いい意味で敷居を低くしたいんです。
「全然敷居は高くないんです。たかがワインですから」と、「されどワイン」って思ってるからこそ、言っていいと思ってて。お店を見ていただくとわかるように、ずいぶんカジュアルでしょう。ワインをカジュアルに楽しんでもらうというのは僕にとってすごく大事なことなんです。




「だだの地下」と名付けられたセラーでは好みの1本に出会える
ありますね。イタリアの生産者から日本はナチュラルワインの世界最大の理解国というか、消費国と思われています。だから、「何で日本でこんなにナチュラルワインが受け入れられているの?」と、よく聞かれます。理由を考えた時に、二つのことが思い浮かびました。
まず一つ目は、昔から複数の宗教が受け入れられている点。仏教と神道がくっついてるお寺もあるじゃないですか。異なる宗教が仲良く暮らせるオープンマインドというか、異文化に対する開けた感覚みたいなものを、日本人はもともと持っていると思うんです。
二点目は、神道です。ざっくり言うと、神道って自然の中にたくさんの神様がいるって考え方です。神が自然を作ったのではなくて、自然の中にたくさんの神様がいるんですよね。創造主がいて自然を創ったのではなくて、自然がたくさんの神を作ったと考える宗教なんです。
台風、土砂崩れ、洪水、地震、津波…自然の超暴力的な部分にさらされることが当たり前で、だから自然を支配しようとしても、そんなことは無理だと日本人はわかっているのかもしれません。
その全てが、ナチュラルワインの世界の当たり前を理解するのに、いろんな手助けをしてくれてるのではないでしょうか。
侘び寂びもそうですよね。朽ちいくもの、壊れるものの中に美を見出す。壊れるからこそ儚く美しい。「自然ってそういうものだよね」という、前提があると思うんです。


敷地内には自然へのリスペクトがそこかしこに
エネルギーのある食べ物や飲み物は、精神にもお腹いっぱい感をもたらしてくれます。もし生きるためだけだったら、カロリーを摂って補助サプリで食生活を補完することもできるかもしれません。でも精神はたぶん、どんどん空っぽになっていくと思うんですね。
心が動くために必要なのは、多分そういうものだと思うんですよ。だから、どんな仕事であれ、自分の小さな世界の中で少しだけ頑張って「俺の仕事もまんざらでもないな」って思いたい。
仕事に貴賎があるのではなく、本人の心持ちの中に貴賎があるんです。「自分もこんなふうに生きたい」「こんな仕事をしたい」と思えるようなきっかけを、僕は素晴らしい仕事をしている人たちから教わってる気がするんですね。
感動と感心の違いは、多分、熱を大きく帯びてるかどうか。僕は自分自身も感動したいし、感動する人の数を増やしたいですね。

太田さんの意思は若いメンバー達にも伝播していく

ワインに出会うまで、自分には主体性も、感性みたいなものもあると思っていなかったんですよ。でも、自分にも感性があるんだと、ワインの世界は気づかせてくれました。僕に「お前にも個性があるんだよ」って教えてくれたのがワインや造り手たちで、僕が僕であることを認めてくれた世界なんです。
だから、いくら「のし」をつけて返しても足りないぐらいです。徹底的に恩を返すつもりで僕は仕事をしたいと思ってます。

以前はAccessを使用した自社開発の受注システムを使用していましたが、事業規模が大きくなるにつれてシステム変更が必要になり、当時システム関連のコンサルタントとして関わってくれていた知人の紹介でGENを知りました。
導入の決め手は、クラウド型であるということ、初期費用が安いこと、カスタマイズを自分たちでできることです。従来型のシステムは自前でサーバーをたて、初期費用に数百万円かかり、細かい変更をするたびに課金されてしまう、ということで当初からそうではないものを探しており、GENの設計ポリシーと自社の運用イメージに合致するところが多かったため、スムーズに導入できました。
クラウド型なので、事務所だけでなくテレワーク時や訪問先でも受注や在庫確認ができるなど利便性が高く、社内外で使いやすいシステムだと感じております。特に各マスタの項目を自分たちで増やせたり名称変更も容易なところに魅力を感じています。
外出先やちょっとしたタイミングでも在庫などを確認したいので、スマホやタブレットでの視認性がさらに向上すると嬉しいです。また、APIを使ったECサイトとの在庫情報の連携、GENのEDIを使ったBtoBのカート運用にも、今後のアップデートで弊社の運用に合う機能がリリースされればチャレンジしたいと思っています。



GEN(ジェン)は事業規模を問わず、様々な業種・業態のニーズに合わせてご利用いただいております。お気軽にご相談ください。スペック表/料金表/各種資料のダウンロード、ShowRoomでの製品デモ予約や無料トライアルも受付しております。
このサイトはreCAPTCHAによって保護されておりプライバシーポリシーと利用規約が適用されます。